今年の数学の問題を解きました。感想としては、

難しい問題と簡単な問題の差が結構あるな~
という印象でした。平均点は去年とそれほど変わらないのではないかと思います。簡単な問題と難しい問題の差が大きく、動揺した人もいるでしょう。その辺も影響して平均点が伸び悩むと思います。
明らかに易化しましたね
という塾の先生のコメントがありましたが、本当に数学を指導しているのかなと疑ってしまいますね。日頃から生徒のことをきちんと見て教えていれば、生徒がどの辺が解けなさそうか予想がつきますよね。明らかに易化したというのは、ただ自分がいかに数学が解けるかを自慢したいだけの人です。私なりに分析をすると、以下のようになります。
大問1
(1)の③は計算ミスに気をつけましょう。
(2)は数学の偏差値45未満の人には少し難しかったかもしれませんが、それ以上の人は解ける問題です。
(3)も(2)同様です。
(4)は①の四分位範囲は簡単なので解けないといけない問題、②は解けない人の方が多い問題です。②の問題を簡単だと言う人は本当に数学の先生をやめた方がいいと思います。だって自分目線だからです。先生なら解けて当たり前、でも実際教えていればこの問題解けない生徒の方が多いでしょう?適当に書いて正解する人もいるので極端に正答率が低いことはないと思いますが、それでも本当に理解して解ける人は全体の30%くらいだと思います(適当に書いて正解する人もいるので実際の正答率は50%前後になるかもしれません)。
(5)の問題は正答率が低いでしょう。カードが8枚と多いので、その分樹形図を考える必要があり、ミスしやすいです。三平方の定理を理解して集中力を維持しないと解けない問題です。問題そのものはそれほど難しいものではありませんが、その辺で間違える人が必ず続出する問題です。
(6)は数学の偏差値が45未満の人は、体が拒絶するかもしれません。数学の偏差値が45以上ある人は解けたと思います。
(7)の作図は難しくなく、どちらかと言えば易しめの問題ですが、回転移動を理解していない人は解けなかったでしょう。数学の偏差値が45未満の生徒は解けなかった人もいたと思います。
大問2
(1)と(2)は簡単な問題でした。ここで点を落とすとちょっと痛いです。
(3)は反比例が突然出てきたので動揺した生徒も多いと思います。平行四辺形は傾きが同じなので、ABの傾きとDCの傾きが同じ=傾き1の直線であり、⊿OCDの面積が24ということを利用して解く問題でした。正答率は低いでしょう。
大問3
(1)は簡単。
(2)は、二等辺三角形の性質で「頂角の二等分線は、底辺を垂直に二等分する」を利用して解くのですが、これがそのまま証明に使われることは珍しく、解けなかった人が多いと予想できます。この問題も
簡単でしたね~
という塾の先生のコメントがありますが、本当に先生やめた方がいいと思います。教えるセンスなし、日頃から生徒のことを見て指導していませんと言っているようなものです。
塾では口酸っぱく、何十回何百回とこの二等辺三角形の性質について言ってきましたが、それでも実際にテストで使って解けた人は少なかったと思います。そしてそのことに気づけない人もたくさんいたでしょう。部分点に期待しましょう。
(3)は難しかったですね。⊿ACDと⊿BEDが相似であることを上手く利用すれば解ける問題です。数学の偏差値が60以上ないと解けない問題だったかなと思います(時間制限がなければ解ける人はもう少しいたと思います)。
大問4
(1)と(2)と(3)までは比較的解きやすい問題だったと思います。(4)から先は、やり方を聞けば理解できる人もいると思いますが、実際に試験の時に解けるかと言えば別問題です。よって(4)から先は正答率が下がる問題です。
全体的に、「簡単!解きやすい!」という問題と「うん?どうやるんだ?」と考えさせられたりする問題がありましたね。その差が大きく感情が揺さぶられる問題だったと思います。動揺した人もいたと思いますが、最後までテスト頑張りました。
テスト大変お疲れさまでした。



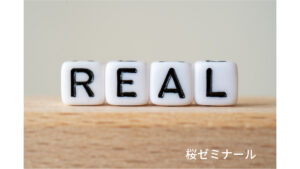






コメント